
年10月24日(水)、16:50~18:30、衆議院第一議員会館の第4会議室にて、「日本の医療の未来を考える会」の第28回勉強会を開催いたしました。詳細は、月刊誌『集中』2018年12月号にて、事後報告記事を掲載いたします。
まず、当会主催者代表の尾尻佳津典より、挨 拶させていただきました。
拶させていただきました。
「今回は政府が推進するAIホスピタルがテーマで、プロジェクトリーダーを務める中村祐輔先生に講師をお願いしました。医療にAIが導入されることに対し、受益者である患者の立場からすると大きな期待を抱いています。」
当会国会議員団会長の原田義昭・衆議院議員は、環境大臣に就任し大臣公務多忙とのことで、勉強会後の懇親会のみ参加されました。
勉強会前には、当会国会議員団の3名の議員からご挨拶いただきました。
冨岡勉・衆議院議員:「本日の辞令で、文部科学委員会の委員長から厚生労働委員会の委員長に横滑りしました。AIによって日本の医療がどう変わっていくのか、シカゴ大学から戻ってこられた中村先生の手腕に大いに期待しております」
三ツ林裕巳・衆議院議員:「厚生労働委員会と災害対策特別委員会で理事を務めることになりました。専門家の方々や各界の方々が集まり、毎月勉強会を開いているのは本当に素晴らしいことだと思います。今日も楽しみにしてきました」
大隈和英・衆議院議員:「中村先生は大阪大学の外科の出身ですが、私も医局の末席におりました。先生の素晴らしい講演は、いつも聞かせていただいています。きょうの勉強会も、AIと医療について大きな示唆をいただけるものと思っています」 今回の講演は、内閣府「AIホスピタルによる高度診断・治療システム」プログラムディレクター、がん研究会がんプレシジョン医療研究センター所長の中村祐輔氏による『医療とAI「AIホスピタル」開発計画~AIホスピタルによる高度診断治療システムについて~』と題するものでした。以下はその要約です。
今回の講演は、内閣府「AIホスピタルによる高度診断・治療システム」プログラムディレクター、がん研究会がんプレシジョン医療研究センター所長の中村祐輔氏による『医療とAI「AIホスピタル」開発計画~AIホスピタルによる高度診断治療システムについて~』と題するものでした。以下はその要約です。
『医療とAI「AIホスピタル」開発計画~AIホスピタルによる高度診断治療システムについて~』
講師・中村祐輔氏
■AIホスピタルにはビッグデータベースの構築が必要
 4月に内閣府のAIホスピタルプロジェクトのプロジェクトリーダーに任命され、その立案から関わってきました。AIホスピタルというと、皆さんいろいろなことを想像されると思いますが、私が考えているのは、AIによって医療現場に人間的な温かさを取り戻す、といったことです。そのようなAIの使い方を考えています。たとえば最近の医療現場では、医師がパソコンを見ながら患者さんと話をすることが日常化しています。電子カルテを記入しなければならないからです。ここにAIを導入し、音声認識のレベルを上げることで、AIが電子カルテを記入できるようになれば、医師が患者さんと目を合わせて会話をする時間を増やすことができます。また、AIはゲノム情報を医療現場に届け、1人1人に最適の医療を提供するのにも役立ってくれます。
4月に内閣府のAIホスピタルプロジェクトのプロジェクトリーダーに任命され、その立案から関わってきました。AIホスピタルというと、皆さんいろいろなことを想像されると思いますが、私が考えているのは、AIによって医療現場に人間的な温かさを取り戻す、といったことです。そのようなAIの使い方を考えています。たとえば最近の医療現場では、医師がパソコンを見ながら患者さんと話をすることが日常化しています。電子カルテを記入しなければならないからです。ここにAIを導入し、音声認識のレベルを上げることで、AIが電子カルテを記入できるようになれば、医師が患者さんと目を合わせて会話をする時間を増やすことができます。また、AIはゲノム情報を医療現場に届け、1人1人に最適の医療を提供するのにも役立ってくれます。
AIホスピタルを実現させるためには、新しい情報社会が必要になります。これまではいろいろな医療情報が、ばらばらに存在していました。画像情報は画像情報だけでデータベース化され、バイタルサインなどは別に保管されていましたし、電子カルテは残っていても、他の情報と組み合わせた形にはなっていませんでした。また、同じ病気と診断されても、患者さんによって多様な疾患背景がありますし、遺伝情報にも多様なバリエーションがあります。そういったことに対し、さじ加減で対応してきたわけです。しかし、膨大な情報をデータベース化してAIを使用すれば、目の前の患者さんにどのような治療が最適なのかがわかるようになります。新しい情報社会では、AIの技術が不可欠なのです。
AIホスピタルでは、病気という枠の中から共通性と多様性を導き出し、その患者さんにとって最適の治療をピンポイントで提供できるようになります。それは、超高齢化社会における医療の質を確保することにも、医旅費の増加を抑制することにもつながります。医療の質を担保しながら、個人にベストの医療を提供するためのAIを活用した医療体制の構築が必要なのです。また、ビッグデータベースを構築することから、いろいろ新しい情報が生まれてくるので、それが新しい診断技術や医薬品の開発につながれば、産業として国際競争力を高めることにもなります。
■医療現場で求められているAIの機能
 AIは正確な画像診断や病理診断のために必要とされています。医療の質を確保する観点からも、AIを活用することが期待されているのです。画像診断や病理診断を行う医師が不足しているので、簡単な診断はAIが行い、グレーゾーンを専門家が診断するようにすれば、時間が確保されて診断の質が上がると考えられます。さらに、遠隔地でも正確な診断を受けることが可能になります。
AIは正確な画像診断や病理診断のために必要とされています。医療の質を確保する観点からも、AIを活用することが期待されているのです。画像診断や病理診断を行う医師が不足しているので、簡単な診断はAIが行い、グレーゾーンを専門家が診断するようにすれば、時間が確保されて診断の質が上がると考えられます。さらに、遠隔地でも正確な診断を受けることが可能になります。
患者さんに起こる危険な兆候を察知することも期待されています。たとえば、患者さんに何か異変が起きたとき、ウエアラブル装置から救急隊に信号が送られるようにすれば、速やかな治療が可能になります。その他、薬剤の誤投与などの人為的ミスを回避したりするのにも、AIを活用したエラー警告システムが役立ちます。さらに遺伝子やゲノム情報を活用するところにAIを使うことで、その患者さんにとって最適の治療を提供することが可能になります。
AIを活用するためには膨大なデータを集める必要がありますが、集積される患者情報には繊細な個人情報が含まれるので、情報管理は重要な問題です。クラウドを利用して1人の情報を分散して管理しておき、バラバラなまま解析していく秘密計算システムの導入が必要だと考えられています。
AIとビッグデータを活用することで、多様な人間と多様な病気に応じた最適医療を提供できるようになっていますが、AIが重要になったのは情報量が膨大になってきたからでもあります。私がゲノムの研究を始めたとき、臨床現場で遺伝子の情報を使うことなど夢のまた夢でした。10年前でも、コストの面から非現実的でした。しかし現在では、患者さんの全ゲノム情報を簡単に調べられる時代になっています。それを取り入れた医療への展開が、アメリカやヨーロッパでは始まっています。ゲノムを読み取るのに必要なコストは、2001年と2017年を比べると100万分の1になっているのです。
■4つのサブプロジェクトがある
AIホスピタルのプロジェクトには、A~Dの4つのサブプロジェクトがあります。
サブプロジェクトAは、セキュリティの高い医療情報データベースを構築することを行っています。病院の情報は非常に複雑で、ベンダーが違うとシステムが異なるため、なかなか1本化できません。その問題を乗り越えて、電子カルテ情報や画像情報など、さまざまな情報を統合して集め、後で解析できるようにしたいと考えています。
サブプロジェクトBは、医師と患者さんが目を合わせて診療できるようにするためのAI活用を目指します。AIが会話を聞き取ってカルテを書いていくのです。音声言語を文章化する技術は非常に進んできているので、それほど難しくはないと考えています。多言語化できれば国際展開することもできます。
サブプロジェクトCは、2種類のプロジェクトが採択されています。1つは血液でがんを診断するリキッドバイオプシーで、これは実用化段階に入っています。これまでのバイオプシーは肺や肝臓などの臓器から組織を採取してきましたが、この方法にはそれなりにリスクがあります。血液だけで診断できれば、合併症のリスクはほぼなく、患者さんにとって負担の軽い検査です。リキッドバイオプシーで難しいのは、得られた複雑なデータをどう解釈するかですが、それにはどうしてもAIが必要になります。
もう1つ採択されたのは、AIがアシストする大腸内視鏡検査です。この検査では内視鏡を盲腸まで挿入する必要がありますが、技術の習得に多くの時間がかかります。この操作をAIがアシストするのです。AIを使うと腸壁を傷つけずに内視鏡を自動挿入できるので、医師は画面に集中することができます。それにより、見落としが防げると考えられています。
サブプロジェクトDは、AIホスピタルのモデルシステムを構築します。最終的にはいろいろな情報を1ヵ所に集中させ、AIが1人1人の患者さんに最適の治療を提供できるシステムを作り上げたいと考えています。現在、国立成育医療研究センターと慶応義塾大学病院で、AIホスピタル機能を実装する研究が進められています。
■AIホスピタルを輸出できる産業に
今求められているのは、日本を医療最先端の国にしつつ、医療費も増加させず、医療従事者の負担も増やさない、ということです。これらを可能にするAIシステムが必要とされています。それには、国ぐるみでAIについて考え、実用化していく必要があります。また、できることならこれを海外に輸出し、産業として育てていくべきであると考えています。
医療情報やゲノム情報のデータベース化も、AIも、国の命運に関わっています。それによって医療における人的エラーが回避できますし、有用情報の発見から新薬や新しい診断法の開発につながることが考えられますし、患者さんに最適で安全な治療を提供することもできます。また、大災害時に個々の患者さんの健康を維持するためにも、とても重要だと思います。こうしたAIホスピタルを実現させることで、21世紀の医療システムの大変革を行っていくべきだと考えています。
質疑応答では次のような発言がありました。
尾尻:「日本はゲノム研究の後進国になってしまったという話がありましたが、以前は先進国だったのでしょうか。なぜ後進国になってしまったのですか」
中村:「我々が遺伝子多型のプロジェクトを進めているとき、そこで使われたデータの約25%が日本のものでした。しかし、その後ゲノム不要論が出てきて、ゲノム研究は10年間の冬の時代を迎えたのです。2001年にゲノムが解読されたとき、アメリカのクリントン大統領や、イギリスのブレア首相がそれを祝福しました。また、オバマ大統領は次々とゲノム医療に関する政策を打ち出し、ゲノム利用を支援してきました。最も大きかったのは、2015年のプレシジョンメディシン・イニシアチブです。これは、ゲノムを通して医療が変わることと、この分野ではアメリカが世界一であることを訴えたものでした。ゲノムの重要性を政治が認識していたかどうか。何が違っていたのかといえば、そこです。2005年まではいい勝負をしていましたが、それ以降、どんどん遅れてしまいました」
 神野正博(日本病院団体協議会議長):「AIホスピタルには、医療費の抑制や医療の質が高くなるなど、いいことがたくさんあるわけですが、これを日本中に広めるとき、その原資はどこに求めるのでしょうか。それによって得をする人が払うとすると、患者さんでしょうか。それとも保険者でしょうか。医療機関でしょうか」
神野正博(日本病院団体協議会議長):「AIホスピタルには、医療費の抑制や医療の質が高くなるなど、いいことがたくさんあるわけですが、これを日本中に広めるとき、その原資はどこに求めるのでしょうか。それによって得をする人が払うとすると、患者さんでしょうか。それとも保険者でしょうか。医療機関でしょうか」
中村:「私は、民間企業が産業活動の一つとしてやっていくべきであると考えています。トータルの医療費が今のままでは、医療保険制度は破綻するでしょう。それを防ぐには、医療費をいかに効率的に使うかが重要です。医療費を増やさないことを目標にするのではなく、医療の質を落とさないために何をすべきなのかを考え、それを産業として回して行けば、企業は活性化して利益を生み出し、利益が税として還元されます。このようなパターンが、国として最も望ましいのではないかと思います。もし日本の企業がやらなければ、外資が入ってくることになると思います」
 加納宣康(医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院院長):「私は長年外科医として自分の手術を自慢して生きてきましたが、今日お話を聞いて、頭をガーンとたたかれた思いです。今まで、ゲノムとかAIなどと聞いても、自分には関係のない話だと思っていましたが、これからは歳をとった外科医も生き方を変えて、もっとマクロ的に医療を見て、貢献していかなければと思った次第です」
加納宣康(医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院院長):「私は長年外科医として自分の手術を自慢して生きてきましたが、今日お話を聞いて、頭をガーンとたたかれた思いです。今まで、ゲノムとかAIなどと聞いても、自分には関係のない話だと思っていましたが、これからは歳をとった外科医も生き方を変えて、もっとマクロ的に医療を見て、貢献していかなければと思った次第です」
 長堀薫(横須賀共済病院病院長):「AIホスピタルプロジェクトに採択され、今年の4月から音声入力ができる電子カルテの開発を進めてきました。現在はどこの急性期病院でも過重労働になっていますが、業務内容を調査すると、たとえば病棟ナースの仕事の3割は記録です。時間外の仕事では、半分以上が記録なのです。それを解決できるスキームは、音声入力ができる電子カルテだと思いました。もし、外来の診察時間を患者1人当たり1分削減できれば、大幅に業務時間を短縮できます。AIにタスクシフトすることで、人件費を下げられるかもしれません。AI導入によって、医療の質を高め、医療従事者の負担を軽減し、財政的な問題の解決にもつながるわけで、まさに一石三鳥の効果があるのではないかと考えています」
長堀薫(横須賀共済病院病院長):「AIホスピタルプロジェクトに採択され、今年の4月から音声入力ができる電子カルテの開発を進めてきました。現在はどこの急性期病院でも過重労働になっていますが、業務内容を調査すると、たとえば病棟ナースの仕事の3割は記録です。時間外の仕事では、半分以上が記録なのです。それを解決できるスキームは、音声入力ができる電子カルテだと思いました。もし、外来の診察時間を患者1人当たり1分削減できれば、大幅に業務時間を短縮できます。AIにタスクシフトすることで、人件費を下げられるかもしれません。AI導入によって、医療の質を高め、医療従事者の負担を軽減し、財政的な問題の解決にもつながるわけで、まさに一石三鳥の効果があるのではないかと考えています」
中村:「ぜひ成果をあげていただきたいと思っています」
 田邉一成(東京女子医科大学病院病院長):「5年後に新病棟を建てるのですが、そこにはかなりAIシステムを導入する予定です。そのとき民間企業とのタイアップは非常に重要だと思いますが、それを進めていくには、どうしてもデータを共有して使わなければならず、そこがなかなかスムーズにいきません。そのあたりについては、国が施策としてやらなければならないと思いますが、そういったことも先生たちのところで考えることになるのでしょうか」
田邉一成(東京女子医科大学病院病院長):「5年後に新病棟を建てるのですが、そこにはかなりAIシステムを導入する予定です。そのとき民間企業とのタイアップは非常に重要だと思いますが、それを進めていくには、どうしてもデータを共有して使わなければならず、そこがなかなかスムーズにいきません。そのあたりについては、国が施策としてやらなければならないと思いますが、そういったことも先生たちのところで考えることになるのでしょうか」
中村:「サブプロジェクトAは、企業とともにデータベースを作ることに取り組みます。もしデータを集められないとしたら、その企業は生き残っていけないことになります。5年間、担保されているわけではありません。見直しが行われるということです」
 井元剛(株式会社9DW代表取締役社長):「AIを開発する側の人間ですが、AIを開発するためにはどうしてもデータを入手しなければなりません。海外では、データを国主導で集めています。サブプロジェクトAに関しては、初めて知ったのですが、いささか旧態依然としたデータベースで、これは厳しいのではないかと感じました。ほかの案件との連携も必要ではないかと思いますが」
井元剛(株式会社9DW代表取締役社長):「AIを開発する側の人間ですが、AIを開発するためにはどうしてもデータを入手しなければなりません。海外では、データを国主導で集めています。サブプロジェクトAに関しては、初めて知ったのですが、いささか旧態依然としたデータベースで、これは厳しいのではないかと感じました。ほかの案件との連携も必要ではないかと思いますが」
中村:「もちろんこれは我々に課されたテーマで、他にもAIを基軸にプロジェクトが走っているわけで、それと連携するように連携会議も開いています。それから、データを集めることに関しては、必要だから出してくれというアプローチのしかたでは、永遠に集まりません。データの中には機微に富んだ情報もあるし、個人のプライバシーに関わるものもあります。データの必要性を訴えて、そのためには皆さんの協力が必要です、と話す姿勢が必要だろうと思います」
 土屋了介(公益財団法人ときわ会顧問):「患者の立場から質問させていただきます。たとえば銀行口座なら、自分の口座がどうなっているかをいつでも見ることができます。患者情報は患者自身の財産でもあるので、いつでも見られないとおかしいのではないでしょうか。私のデータなのだから、病院の許可などなしに、いつでものぞけないとおかしいのではないか、と思うのですが」
土屋了介(公益財団法人ときわ会顧問):「患者の立場から質問させていただきます。たとえば銀行口座なら、自分の口座がどうなっているかをいつでも見ることができます。患者情報は患者自身の財産でもあるので、いつでも見られないとおかしいのではないでしょうか。私のデータなのだから、病院の許可などなしに、いつでものぞけないとおかしいのではないか、と思うのですが」
中村:「おっしゃる通りだと思います。どこまでが患者さん個人のものなのかを、もっとオープンに議論していかなければならないと思っています。少なくとも診療情報は、患者さんが自由に見ることができるべきだと思いますし、そこまでできればいいと思っています」
 瀬戸皖一(一般社団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院口腔がん治療センター長):「本日のお話で、わが国が遅れたままなのだということを認識させていただきました。この際、国際連携をやった方が手っ取り早いのではないかと考えています。日本の私立病院は一般企業との連携を取りにくい状態ですので、むしろ国際的に連携したほうがいいのではないかと思っています。しかし、国際連携もなかなか取りにくい状態にあると認識しています。その点についてはどうお考えですか」
瀬戸皖一(一般社団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院口腔がん治療センター長):「本日のお話で、わが国が遅れたままなのだということを認識させていただきました。この際、国際連携をやった方が手っ取り早いのではないかと考えています。日本の私立病院は一般企業との連携を取りにくい状態ですので、むしろ国際的に連携したほうがいいのではないかと思っています。しかし、国際連携もなかなか取りにくい状態にあると認識しています。その点についてはどうお考えですか」
中村:「私は国際連携が難しいとは思っていません。東アジアや東南アジアから見れば、日本の医療の質はあこがれの的ですから、できないことはないと思います」










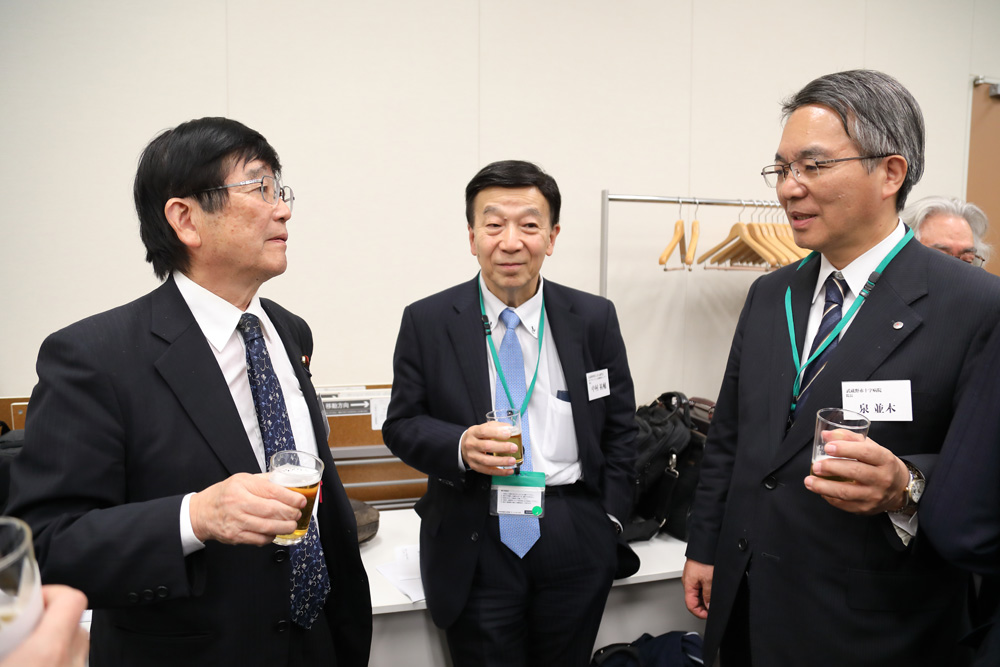








LEAVE A REPLY